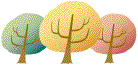
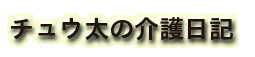

2003年6月23日 沖縄慰霊の日
根室にお住まいの見知らぬ女性の方からメールをいただきました。私の著書 和子 アルツハイマー病の妻と生きる をお読みになってお便りをくださったのでした。小学校の教師をなさっているようですが、「なんて心豊かに生きていらっしゃることかと思いました」 とありました。そして、「学生時代、ほんの少し声楽をかじったものの、ここ数年地域の合唱団も休眠状態の私。ガーンと頭を打たれた気がしました。『たくさん歌いなさいな』と和子さんに言われた様に思いました」 と。
病気は重度になって、今は半分寝たきり状態だけど、そんな状態になっても精神的に豊かな生活が出来ていること、そして和子が 『たくさん歌いなさいな』 と、人を励ます力を持っていることに、夫冥利に尽きる思いもあります。
勝手に引用させてもらったついでに書けば、その方の隣に私の南高教師時代の教え子が教師として住んでいるというのも驚きました。彼とはよく付き合ったので、新婚時代の私の家にも来ていた筈だから、和子のことも覚えているでしょう。根室と札幌という何百キロの距離を、インターネットの世界は隣に居るように近づけてくれます。
私が15年間教師生活を送った札幌西高の同窓会館に、和子のグランドピアノを寄付したのは2000年の春でした。そのピアノを使って西高OB合唱団が1年間練習を積み、翌年8月、OBオーケストラと一緒にベートーヴェンの第九演奏会を開きました。若干の賛助出演の方たちも含めて全員が会費を払って参加し、壮大な舞台を作りました。私も小樽から練習に通いました。ソリストも含めて全くの自まかないの演奏会だったけれど、ドイツ語の発音も発声も団員の中のプロの指導で、みっちりたたき込まれました。1年後の去年8月、和子のピアノに金属エッチングのプレートが取り付けられました。
和 子 の ピ ア ノ
輔仁会と妻への想い
旧職員 後藤 治
和子のピアノは、同窓生の中の調律師の手でいい状態に保たれ、西高の音大受験生や、OB・OG関係者のオペラ練習にまで順番待ちで使われていると聞きました。
そして5月、うれしい連絡が届きました。「西高メモリアル合唱団」の結成の案内です。来年8月の西高OBオーケストラ第20回定期演奏会に賛助出演、ヨハン・シュトラウスの「美しき青きドナウ」を歌うことになり、6月から月1回の練習が始まりました。夜は和子のケアは入らないので、ナースに頼んで時々看てもらうことに了解を取りました。和子は時々痰の吸引が必要なので、誰にでも留守番を頼むわけにいかないのです。こんなことで、ともかく毎月和子のピアノに出会えること、そのピアノを使って合唱の練習に参加できることに浮き立つ思いがあります。
マンションから車椅子を押しながら歩いて15分足らずの所に、北海道立近代美術館があります。雨が上がってすっきりと晴れ上がった土曜日の午後、ふと思いついて足を延ばしました。いまここで特別展 「安田侃の世界―天にむすび、地をつなぐ―」 が開かれています。安田侃(かん)氏は北海道美唄市の出身で、白大理石産地イタリアのピエトラサンタで彫刻を続けている人です。
和子の身体障害者手帳を見せたら、本人と付き添いの私の二人とも無料で入場できました。晴れた土曜日の午後なのに会場は空いていて、車椅子を押してゆっくり回れました。白い大理石とブロンズの抽象彫刻は、なだらかな曲線で覆われ、生命が息づいているかのように思われました。和子の反応は聞けないけれど、美術館が好きだった和子なので、これからも連れて行きたいと思いました。
彼の故郷・美唄市の炭坑小学校の廃校舎内外には、既に1992年から彫刻が設置され、「アルテ・ピアッツァ美唄」として整備がすすめられ、今度の特別展はその美唄の会場と同時開催になっています。
美唄市は私たちが出会ったマチ、そして炭坑閉山のさなかにあって和子が4年間音楽教師として住んだマチです。いつかお天気のいい日に連れて行きたいと思いながら美術館をあとにしました。
関連していろいろなことを考えました。前回書いた国立大学法人法案のこと。延長国会になって、まだ参議院で審議中です。ほとんどマスコミが報道しないこのニュースを、東京新聞が報じました。
『東京新聞』2003年6月21日付 『核心』
|
国立大学法人化、文科省立ち往生、参院で「まさかの抵抗」法案審議ストップ10日大学への資料提出指示「国会軽視の事前介入」、文科相謝罪で打開の道探る 文部科学省が参院の抵抗に遭って立ち往生している。来春の国立大学法人化に向け命運をかける「国立大学法人法案」の参院審議で、遠山敦子文部科学相が答弁に窮して今月十日から審議がストップしたままなのだ。法人化後に各大学が定める中期目標や計画について、同省が法の成立前に詳細な資料提出を大学側に「指示」していたことが発覚し、追及側は「国会軽視の事前介入だ。審議未了で廃案へ」と気炎を吐く。一方、追い込まれた文科相は来週、答弁を訂正する異例の「おわび」で空転打開を図るが、すんなり再開となるか。(社会部・佐藤直子) |
国立美術館と博物館の独立行政法人への移行は、反対の声を無視してさっさと強行されました。「“親方日の丸”でなく、経費は自分で稼げ」 ということだったと、私は勝手に解釈したけれど、どの館も収益を揚げるのに苦労しているようです。和子の病気がわかったあと私たちが出かけたロンドンやパリ・ニューヨークの美術館は無料か日本とは比較にならない低い料金でした。学問や文化・芸術は、国や自治体の予算でやるものだと思っています。そのうちに図書館まで独立行政法人でやれと言い出すのではないか、とあらぬことを考えました。図書館が有料になったら・・・というのはブラックユーモアの世界です。そんなに独立(特別)行政法人にしたかったら、警察や消防も独立採算の法人にしますか。
東京都三多摩地区の中都市で図書館長をしている教え子からメールがきました。
|
先生の本を私の勤務する図書館で受け入れたのは昨年の5月はじめ頃、利用者のリクエストでした。朝日新聞の書評から2週間後ぐらいだったでしょうか?先日、もう1年たったんだと思い、本の貸出データを見てみました。昨年度8回、今年度2回の計10回貸出となっていました。スゴイと思いました。置いてある棚は「916」、手記・ルポルタージュを著者の氏名の50音順に並べています。背中が並んでいる棚の中で、率直に言って名も知られない著者の本がこんなに動くとは!!残念ながら読んだ人の反応をお伝えできないのは今の図書館の限界のひとつですが・・・ とりあえず、先生の本のことをお伝えしたくてメールしました。 |
思いがけなく朝日新聞の書評に取り上げられて、あちこちの図書館で入れてもらいました。たくさんの方たちが読んでくださったようです。それから1年あまりたち、和子の病状もずいぶん変化したけれど、私たちは希望を持って生きています。
