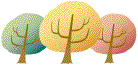



2001年6月23日
梅雨前線が北に上がって、北海道もここのところ梅雨空が続きます。北海道には梅雨がないというのは昔の話で、ここのところ毎年この季節は天候不順です。今年は6月半ばを過ぎてもストーヴを焚いています。テレビの気象予報士は、「えぞ梅雨(つゆ)の梅雨寒(つゆざむ)」と言っています。7月になれば北海道らしい素敵な夏がくるでしょう。 和子がホームに入所する前は、この季節は洗濯物が乾かなくて困ったことを思い出します。あれからもう満2年が過ぎました。
梅雨に入る前の週末に、ニューヨークから賓客が和子に会いに来ました。アフリカのガーナ出身の青年Gです。
1989年秋、JICA(国際協力事業団)の奨学資金で北大の農学部に畜産の短期研修にきていたモーリシャスの青年Vが、札幌の国際親善団体の紹介で、「帰国前の1泊のショート・ビジット」で私たちの家に泊まりにきました。彼は殆ど日本語ができなかったけれど、私は辞書を引きながら片言の英単語で何とか意志疎通をし、ミッションの大学出身で、きれいな英語の発音ができた和子とは、少しは会話らしいものになりました。その時の写真を大急ぎで現像して、帰国前の彼のホテルの部屋に届けたとき、その部屋で彼から「友人です」と紹介されたのが、そのガーナの青年Gでした。彼らは英語のネイティヴ・スピーカーでした。インド洋上のアフリカ大陸に近い島国のモーリシャス共和国は1968年に英連邦内で独立した多民族国家で、彫りの深い顔をした彼はインド系でした。ガーナも1960年イギリスの保護領から独立した新しい共和国です。
Gは文部省の給費留学生で、北大の農学部大学院に農業土木の研究にきたばかりでした。大学院の修士・博士課程で6年がかりで勉強をするという、その研究生活の1年目でした。来日当初、日本語の学校に通った彼は、日常会話に不自由しないほどの日本語が出来ました。 それ以来、私たちが札幌を離れるまでの2年半の間に、彼は何度も我が家に泊まりがけで来ました。その間には、札幌のテクノパークにコンピューターの短期研修に来ていたシンガポールの女性技術者Sが何度かきてくれました。シンガポールは1965年英連邦の一員としてイギリスから完全に独立した國です。英語のヒアリングがロクにできない私は、中国系の彼女とは辞書をを引くより漢字の筆談の方が意志疎通ができました。彼と彼女は英語で流ちょうに話し、会話に入れない私に和子が笑いながら少し通訳してくれたりしました。 登別の養魚場に家族みんなと鱒釣りに行って、そこで釣ったばかりの鱒料理を食べたり、ちょうどお雛祭りの時期で、和子が彼女に着物を着せて、お雛様の前で写真を撮ったり、うちの子ども達も入れて3っつの国籍の人間が集まって、こころ愉しい日々でした。 シンガポールのSが何度か訪ねてきた最後の頃、私は聞きにくかったことを初めて口にしました。前の大戦で日本軍がシンガポールを占領していた頃、彼女の肉親で被害にあった方は居ないのかと。居ないという答えを聞いて、ホッしたことを忘れません。南京大虐殺ほど知られていないけれど、1941年12月の太平洋戦争開戦当時、いちはやく無血占領した日本軍が、スパイ容疑ということで、たくさんの民間人を連れ去って、その人達の多くが2度と帰って来なかったという話を、本で読んだりテレビのドキュメンタリーで見ていました。 あとから、もし肉親に被害を受けた方がいれば、多分そういう方は日本に研修に来たりはしないだろうと思いました。35歳ぐらいだった彼女は勿論大戦時は生まれてなかったけれど、両親や祖父母や親戚の方に被害者がいても不思議ではありません。 Sがシンガポールに帰国したあと、私たちが札幌を離れるまでの1年間、Gは何度も家に来ていました。'90年の秋、私が卒業した大学の男声グリーのOB演奏会にも来てくれました。その年の暮れ、私が胸に異変を感じ、入院して心臓カテーテル検査の結果、異型狭心症と診断が出ました。そして勤めていた子ども図書館の仕事を片づけ、札幌を引き払う準備をしました。3月末に検査から退院した頃、札幌の東海大学から、アメリカからの留学生のホストファミリーを引き受けないかと打診ががありました。大学が同じ南区で、わが家から自転車で15分ぐらいで大学に通える距離でした。札幌の最後の年だし、3ヶ月間という初めての長期間のホームステイだったけれど、和子が乗り気だったので引き受けました。わが家に現われた初めての白人青年Mでした。彼のために一室を空け、私と和子と高校生の次男とMと4人の生活が7月まで3ヶ月続きました。ガーナのGも来て、ピクニックに行ったことも楽しい思い出です。
'91年夏Mは留学プログラムが終わってアメリカに帰国し、翌年3月、私たちはGに見送られて東京に引っ越しました。東京に行って間もなく和子の様子が普通でないことがはっきりして、いろいろなことが続き、専門の病院で理学検査の結果、12月にアルツハイマー病中期症状だと診断が出ました。ドクターから、「一緒にいて気が付かれませんでしたか」問われました。そういえばMがホームステイしていた3ヶ月間、彼女は家事が出来なくなっていたなあと思い当たるけれど、「長年の共働きで疲れが出たんだろう」と思っていた私が、その分を補っていて気付かなかった迂闊さを、あとから後悔しました。そんないきさつの一部は『介護日記』の冒頭に書きました。
モーリシャスに帰国したV、シンガポールに帰国したS、アメリカに帰国したMとは、和子が英語で文通していたけれど、私は英語の手紙を読めても返事を書けず、まして和子の病気を伝える術もないまま、3人とも音信が途絶えました。どうして手紙が来ないのだろうと、いぶかっているだろうとは思ったけれど、どうしようもないままでした。 和子が日野の姉の家に泊まりに行った留守に、札幌のGのアパートに電話をしたのですが、半年前まで彼が「ママ、ママ」と親しんでいた和子が、アルツハイマー中期症状だとは、彼はにわかには信じがたい様子でした。彼は研究生活は英語で済んでいたので必要に迫られなかったからか、漢字まじりの日本語の手紙は読めませんでした。
'94年春、私達が小樽に戻って来たとき、訪ねてきた彼がフト漏らしたことが忘れられません。農業土木の研究の中身は私も理系の人間だから、おおよそのこと聞いて判ったのですが、その時彼が初めて口にしたことに驚きました。指導教官の指導の下に5年間研究し続けた研究のデータが、学会や雑誌で何度も発表され論文になっても、1度も彼の名が共同研究者として紹介されたことがない、という話でした。そして間もなく彼が札幌の研究生活に見切りをつけ、ニューヨークに飛んだと、本人からいきなり電話を貰って絶句しました。ドクターコースに進んでいた彼には、文部省の給費留学生としての身分が保証されていたのに、その身分を捨てての転身でした。小樽に訪ねて来たとき、彼は多くを語らなかったけれど、有色人種に対する差別だとしか考えられず、日本人の一人として恥ずかしい思いをしました。 ニューヨークから、時々電話や絵葉書がきました。和子がショートステイで留守の時には、少し詳しく病気の進行の状況を話しました。でも書き続けてきた『介護日記』の中身を全部、電話で話すことなど不可能でした。和子の“暁の脱走”のことも知りません。レーガン元大統領の発病のニュースを彼は知っていました。 少し前、インターネットを始めた彼からは、私にも判る易しい英語でメールがきて、私はローマ字で返事を送っていました。ニューヨークのブロンクスに住み、労働をしながら金を貯め、いま大学で薬学を勉強しています。永住権もとり出国ビザが取れたので、7年振りに旧知を尋ねて札幌にきたのだそうです。日程が決まってから、「Japan Visit 」というタイトルで、「Hello Papa! 」とメールが届きました。こんな時、インターネットの途方もない便利さを実感します。時差はあるけれど、地球の反対側と瞬時にメールのやりとりが出来ます。 今回の止宿先の、札幌の国際親善団体のOさんが、車で彼を連れてきて下さいました。前夜お電話を頂いたとき、和子の病気のことを手短にお話ししました。その日はホームで落ち合い、和子を車に乗せてダム湖園地に行き、Gが車椅子を押して、ゆっくり散歩を楽しみました。7年前に別れた彼を和子が覚えて居るはずはないのだけれど、和子はずっと愉しそうでした。普通の意味で言う“記憶”とは別の、感性の領域の記憶があるとしか思えません。
今になって思うけれど、和子は肌の色の違いによる人種的偏見など、露ほど持ち合わせていない人でした。私は「差別はいけない」と構えたところがあったけれど、和子は全く自然で、初めから旧知の友人を遇するようでした。
ダム湖園地を一緒に散歩しながらOさんが、「Gは奥さんの病気のことを、おおよそ理解しているようですよ」と仰言いました。7年振りに海の向こうから訪ねてくれた彼と、こんな再会は辛くはあるけれど、でも笑顔いっぱいの和子と過ごして、写真も撮ったし、彼も多分納得してくれただろうと思います。
東京の医師から「発病後、5年は経っている」と言われたけれど、和子が、モーリシャス、ガーナ、シンガポール、そしてアメリカと4カ国もの青年達を、ホストファミリーとして受け入れてきたのは、彼女の、「生きる意志」だったようにも思います。ヤマハの教師は私が室蘭にいた間に体を壊して辞めていたし、自宅レッスンに通ってくる子ども達はもう少なかったのです。私は一応仕事に出ていたし、彼女は客人を迎えて接待をするのは自分の仕事だと思っていたのでしょう。
前に書いたけれど、吉目木晴彦の『寂寥郊野』に、女主人公の、記憶が薄れていく不安が、リアルに描かれています。和子もそんな不安と必死に闘いながら、外国の青年達との日々を紡いでいたのだろうと思います。ガーナの彼が訪ねてくれて本当に良かったと、少し安堵の思いです。
